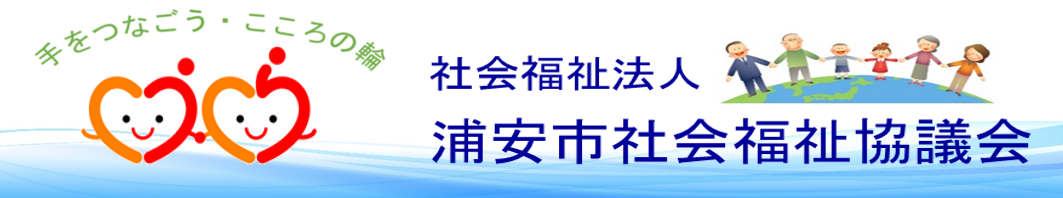社会福祉協議会支部(略称:支部社協)活動の拡充
社会福祉協議会支部事業
社会福祉協議会支部の行っている主な事業を紹介します。身近な地域における福祉活動として「住み続けたいと思える地域をつくるために」をテーマとして、取り組んでいます。
-
- ふれあいサロン・子育てサロン
支部社協が取り組んでいる地域支えあい活動の一つで、高齢者、障がい者、子育て中の方が住み慣れた地域でいつまでも安心して生活できることを目的に行っています。
地域住民同士が交流を深めることで、地域の中で顔見知りの関係ができ、孤独、閉じこもりの防止等の効果が期待されています。
-
- 高齢者等対象のバスツアー
外出することが少なくなった高齢者などを対象として、外出する機会を設けるとともに地域の方々との交流の場づくりとしてバスツアーを実施しています。
-
- 健康教室・福祉講座などの開催
健康づくりは、生きがいのある生活を送ることと直接つながることから、健康な体を維持していくための体操などを取り入れた健康教室や健康をテーマにした講座を開催しています。
また、介護保険制度や相続・遺言など身近な課題をテーマとした講座を取り上げ地域で開催しています。
-
- 地域行事や福祉教育への参加・協力
自治会祭りや小中学校、保育園における行事に参加協力しています。
また、支部社協ごとにちょっとしたお手伝いが必要な方へのたすけあい活動や、声かけ活動などをはじめさまざまな取り組みが実施されています。
福祉教育の推進
福祉教育の目的は、子どもたちが高齢者や障がいのある方など生活ニーズのある多くの地域住民と出会い、ふれあいの中からその生活課題を自分のこととして共有し、解決する方法を自ら導き出す「共に生きる力を育む」ことにあります。そして、子どもたちがそれぞれの住む地域でその力を発揮し、人に優しい活動を始めていくことで、誰もが自由や尊厳を奪われることが無く、幸せに暮らせる街づくりへとつながります。
そのため、社会福祉協議会では、学校と福祉関係者との連携のもと、多くの子どもたちに、障がいのある方や高齢者の暮らしや地域の福祉課題・生活課題について学ぶ機会を提供し、子どもたちの問題解決能力の向上とノーマライゼーション意識の醸成を図っています。今後も、学校・家庭・地域社会が協働して福祉教育プログラムを作成・実施する等、皆で子どもを福祉のコミュニティづくりの担い手へと成長させる取組みを進めてまいります。
○千葉県指定福祉教育推進校
平成19年度から、推進校間の連携を図るとともに、子どもの発達段階に応じた福祉教育の実践をより効果的にすすめるため、中学校区の小・中学校をパッケージで指定し、併せて近隣の高等学校も指定することとしています。また、学校と地域との連携を図りながら福祉教育を効果的に推進するため、中学校区指定校が所在する社会福祉協議会支部を福祉教育推進団体として併せて指定することとしています。
(平成19年度~指定)
・東海大学浦安高等学校
(平成20年度~指定)
・浦安市社会福祉協議会東1支部(美浜地区)
・千葉県立浦安高等学校
・浦安市立美浜中学校
・浦安市立美浜北小学校
・浦安市立美浜南小学校
(平成21年度~指定)
・東京学館浦安高等学校
(平成25年度~指定)
・浦安市社会福祉協議会南2支部(東野・弁天地区)
・千葉県立浦安南高等学校
・浦安市立見明川中学校
・浦安市立見明川小学校
(平成30年度~指定)
・浦安市社会福祉協議会南1支部(東野・富岡・今川地区)
・千葉県立浦安高等学校
・浦安市立富岡中学校
・浦安市立東野小学校
・浦安市立富岡小学校
・東海大附属浦安高等学校中等部
○浦安市社会福祉協議会指定福祉教育推進校
千葉県福祉教育推進校の活動をさらに発展・継続させることを主たる目的として、浦安市社会福祉協議会による指定を行っています。
(平成19年度~指定)
・浦安市立日の出南小学校
(平成22年度~指定)
・東海大学浦安高等学校
・浦安市立浦安中学校
(平成23年度~指定)
・浦安市社会福祉協議会東1支部(美浜地区)
・千葉県立浦安高等学校
・浦安市立美浜中学校
・浦安市立美浜北小学校
・浦安市立美浜南小学校
(平成24年度~指定)
・東京学館浦安高等学校
(平成28年度~指定)
・浦安市社会福祉協議会南2支部(東野・弁天地区)
・千葉県立浦安南高等学校
・浦安市立見明川中学校
・浦安市立見明川小学校
ボランティアセンターの運営
ボランティアをしたい人と、お願いしたい人(依頼者)とをつなげる機関として、ボランティアの情報や福祉体験の場の提供、相談への対応、福祉教育の協力などの取り組みを進めます。
災害ボランティアセンターの運営
災害時における災害ボランティアセンターの設置場所が浦安市交通公園に決定したことにともない、災害時に効率的な運営ができるよう、活動資機材等の整備や運営体制の整備を図ります。また、災害ボランティアコーディネーターの養成に取り組みます。